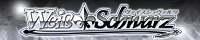陸地から見た景色。
一面を青に染める、惑星クレイの美しく広大な海原。微動だにしない水平線。
時が止まったかのようなその光景を、

「ッシャア!コイツで10体目ェッ!3点差だぜパヴロス!」
「先走るなラビス!これは戦だ!競ってるわけじゃないんだぞ!」

爆音と水柱が破壊した。

「伍長が誰かの単独行動を注意する日が来るなんて…」
「ソティリオ。感動するのは一向に構わないけど――」
「――戦場で足を止めるな。もちろんわかってるよ、オデュッセウス」

今、この海域は、海軍“アクアフォース”とアンデッド海賊団“グランブル―”の一団によって、
血飛沫ならぬ水飛沫が舞い上がる戦場と化していた。戦況は海軍側が優勢。劣勢の海賊側は、
すでに片側の船の半数以上が沈没し、渦に呑まれている。

「我が軍は優勢、か」
「ええ。この後の敵の出方次第ではありますが…」
「このまま押し切ってしまえそうな勢いだがな」
「大佐。油断・慢心は忌むべき幻想です」
「私が気を抜いた分、お前が気を張ってくれるから問題無いさ。頼りにしているぞ、ミルティアディス」

兵の数は大して変わらない。だというのにこれだけ戦況が偏るのはなぜか。
兵士の技能水準が高いことはもちろんだが、最大の理由は優秀な「軍師」がいることだろう。

「さて…海中の部隊から何名か偵察にまわしてくれ。敵伏兵の潜伏先を探る」
「はっ、ソティリオ兵長をはじめ、偵察に適した技能を持つ将兵を選定しましょう」

《轟く波紋》の異名を持つ海軍大佐「ジノビオス」。この部隊の長にして、
アクアフォースでも1、2を争う名軍師。
海軍大将「メイルストローム」からの信頼も厚い、心優しき絶対正義の提唱者。

「人選はお前にまかせる。報告次第では全軍に突撃命令を出すつもりだ。いつでも陣形を動かせるよう、必要な者には伝令を飛ばしておきたいところだが」
「敵は浮足立っています。陣形の変化ですら気づく確率は低く、ましてや伝令によるこちらの微細な動きを警戒される可能性は皆無といっても良いでしょう」

全幅の信頼を寄せる副官に、無言で頷きを返すジノビオス。
即座に動きだしたミルティアディスから目を離し、再びブリッジのモニターで状況確認を行う。
「何も無ければそれで良し。だが、私の読みが正しければ……」
戦は、佳境を迎えつつあった。



うってかわって海賊側――後部中央に位置する、ひときわ巨大な船の船長室。
その豪勢な扉を蹴破り、1人の女海賊が中に飛び込んできた。

「ノワール!左側のヤツらが軒並みやられちまった!まずいよ!」
「そうかいそうかい、召集に応じようとするとロクなことにならないね。しかしまずいなぁ。困ったね」
「余裕かましてる場合じゃ……」

“グランブルー”所属の船長が1人、「ピノ・ノワール」は、第一の部下である
「ピノ・ブラン」の切羽詰まった伝令を聞いても、常の通り落ち着いた笑顔を
崩さなかった。彼は決して無能ではない。その眼に刺すような鋭い光が宿って
いることを感じたブランは、言いかけた文句を飲み込んだ。戦況が兵の士気を
大きく左右することなど、当然ノワールも承知している。

「アクアフォースの活動範囲がこんなに広がってるとは思わなかったし…しょうがない」

肘掛けから手を放し、重い腰を上げ、

「ボクが出るよ」

戦況が動く。



「刃が通らねぇだとッ!?」
「斬撃だけではありません。アクアライフルによる狙撃もすべて無効化されています」

敵の伏兵は大した数では無かった。伏兵の居場所がわかり、奇襲を受ける恐れも無くなった今、
このまま押し切ってしまえる――そうなるはずだった。

「アハハハ、キミたち弱いねぇ」
「さスガ船長!ヤっちまッてくダせぇ!」
「…それに負けるキミたちはもっと情けないけどね…あとで覚悟しとくように」
「ヒィィィィィ!?」

ピノ・ノワールは“グランブルー”の全団を束ねる船長「ナイトミスト」と同じ、
強大な力を持つヴァンパイアの1人であり、美しい女性の生き血を至上の宝と豪語する大海賊。
その被害者は数千にまで昇ると言われている。生物の血液中に内包される魔力を力に変えるのが
クレイにおけるヴァンパイア共通の特徴であり、ピノ・ノワールもその例に漏れない。
そう、彼の体は常に、幾重にも張り巡らされた強固な結界で覆われているのだ。

「後退しろ、ラビス!そいつにお前の攻撃は通用しない!」
「うるせェ!やられっぱなしで引き下がれるかってんだッ!」

魔法弾の雨の中を無傷で歩いて行けるほどの強固な防壁を、一海兵の斬撃で破壊できるはずもない。
結界を破るには、規格外の力が必要だった。

「やぶれかぶれって言うのかな。そういう戦い方は美しくないね」
「グァァッ…!」
「ラビスッ!!」
「次はキミかな?」

深手を負ったラビスに気を取られたパヴロスを、ノワールの斬撃が襲う。
その剣がパヴロスのコアを貫く――
ギィンッ!!
――寸前で、ノワールの剣は止められていた。両者の間に投げ込まれた、巨大な光剣の刃によって。
剣の飛んできた軌跡を頼りに、パヴロスは顔ごと、ノワールは目だけをそちらに向ける。

「……真打ちの登場って感じかな」

視線の先にいたのは、静かながらも怒りの表情を隠さないでいるジノビオスの姿だった。
深手を負ったラビス、甲板で事切れている幾人かの海兵たち、最後に焦燥を隠せないパヴロスを見て、
彼は再びノワールに視線を戻す。

「部下が、世話になったようだな」
「なに、世話ってほどでもないさ」

こちらに向かってジノビオスが1歩踏み出した瞬間、ノワールはパヴロスから離れ、
大きく距離をとった。彼が自身の結界を破るに至る、規格外の相手だということを察したのだろう。

「強いね、キミ。アクアフォースの中でも1,2を争うんじゃない?」
「私は生粋の軍師だ。単純な戦闘技術だけを見るのであれば、軍の中では五指にも入らない」
「それはそれは……」
「あまり、我らを舐めないでもらおう」

冗談めかした返しをしたものの、ノワールは内心おどろいていた。これだけの威圧感を放つジノビオスが
戦闘特化の戦士ではなく、さらに“アクアフォース”全体で見れば五指にすら入らないという事実。
自分が放蕩している間に、彼らがどれだけの力を取り戻したのか、想像するだけで冷や汗が伝いそうになる。

(とはいえ、ここにこの男以外の脅威はない…隙を見てナイトミストの船団に合流できれば)
「そして――」

戦艦の周囲に幾つもの水柱が上がったと同時に、目まぐるしく巡っていたノワールの思考が停止する。
まるで、「何を考えているのか分かっているぞ」とでも言うかのようなタイミングで。

「お前がここに出てきた時点で、この戦の勝敗は決した」

水柱はジノビオスを中心に円を描いて立ち並び、竜巻のようにうねりだす。
そして、巻き上がった竜巻の1つがジノビオスの正面に叩きつけられ、爆ぜた。
ここで、ノワールはついに驚きと焦りを顔に出してしまう。
それだけの脅威が、ジノビオスをも凌ぐ強大な何かが、そこに現れたからだ。

『第九侵海迎撃部隊「ジノビオス」隊隊長、海軍大佐ポドロモス。ここにあり!』
「放蕩生活が過ぎたようだな、海賊貴公子。これが超越、正義を為すための新たな力だ!」

さらに、残った無数の竜巻がポドロモスの頭上で陣を描き始める。
幾本もの竜巻が互いに絡み合い、線が増える度に光を増していく。
その輝きが最高潮に達した時、完成した陣の中から姿を見せたのは、見たこともない形状の、巨大な砲門。

「そのまま後方に控えていれば、お前や側近が離脱することはもちろん、部下へ退避を促すこともできただろう。だが、もう遅い」
「……!ブラン、グリ!逃げ――」

電流のように体に流れた滅びの予感が彼を振り返らせ、部下の名を呼ばせる。
危険を省みず敵に背を向けたノワールを追うように、2つの無情な号令が大海原に響き渡った。

「裁きの時だ、ピノ・ノワール!その身に宿す幾多の報われぬ魂と共に、大海へ還るがいい!」
『ニューハイドロエンジン・フルバースト!重機動戦艦全砲門開放!!撃てーーーッ!!』



海につかの間の平穏が訪れた。ピノ・ノワールの船団は9割以上が消滅。彼自身の消息は不明だが、
たとえ消滅を免れたとしても、再びこの規模の戦力を整えるには相当の時間を要するだろう。
討伐に参加した部隊の面々も、休養・訓練など、傷の治療を終えた者から普段通りの生活に戻り始めていた。

「まったく、ラビスめ…。無茶ばかりする」

医務室で豪快なイビキをたてて眠るラビスを見てぼやくパヴロスに、

「伍長も途中までは一緒になって独断専行してたんですから、人のことは言えません」
「んぐッ……」

ソティリオの正論が突き刺さる。

「…すまない。それに関しては自分にも責任がある」

息を詰まらせるパヴロスの後ろで、線の細い青年が壁に寄りかかるように立っていた。パヴロスを茶化すだけのつもりが、思わぬところに飛び火してしまい、ソティリオは珍しく焦った顔を見せる。

「い、いえ…オレストさんのせいじゃありませんよ。伍長たちが勝手にやったことですし」
「彼の力をより生かせるようにと、突出を促すような剣を教えてしまったのは、指南役である自分の落ち度だ。目を覚ましたら、改めてきつく言っておく」
「そこはよろしくお願いします。ボクも伍長にきつく言っておきますので」
「おまえ…一応オレは上官なんだぞ…」




機動戦艦の一室に、入室許可を求める電子音が響く。
モニターに映し出された「アレックス」の姿を見て、ジノビオスはセキュリティを解除した。

「失礼します」
「それでは大佐、私はこれで」

入室直後、敬礼の姿勢を取るアレックスに、退室するミルティアディスもまた小さく敬礼を返す。
その姿がドアの向こうに消え、ロックがかかるのを確認した後、アレックスはジノビオスに向き直った。

「ご報告します。船底の修復、完了しました」
「ご苦労だった、アレックス」

“アクアフォース”の古い艦船は、船底付近にハイドロエンジンに関連する重要な機関があるものが多い。
衝撃耐性の低い、当時の機関の強度を考慮した設計である。
反面、いざ船底付近に損害があると修復も命がけとなる。衝撃で爆発する恐れがあるからだ。
最新鋭の機動戦艦であればそういった心配も無いが、そうそう部隊の艦船すべてを更新できるわけもない。

「船底以外の修復作業はご命令通り、工作科および技術科に引き継ぎました。以降は定期的に、彼らから状況の報告があります」
「そうか……船底の修復は何かと事故が多い。お前たちばかりに頼ってしまって、すまないな」

アレックスとその同世代の兵士たちは、共通の特徴を持つ。強い力を保有するアクアロイドの細胞から
生み出されたこと。そして、体を構成する水分の割合が98.5%以上と極めて高いことである。
水に溶けるその体は、打撃はもちろん爆発などの衝撃全般に強い。
旧式艦の船底修復でいらぬ犠牲を出さないために、彼らに作業を任せるというジノビオスの判断は理に適っている。

「……そのお言葉をいただけただけで十分です。それでは、失礼します」

軍帽を脱いで小脇に抱え、深く頭を下げるアレックス。
最敬礼の間、彼が微笑んでいたことに、果たしてジノビオスは気づいただろうか。



数日後、ジノビオスの指揮する機動戦艦のブリーフィングルームに、多くの将兵が集っていた。
これまでに類を見ない大規模な海賊の船団が迫っている――ピノ・ノワールの撃破は、
“グランブルー”の全団を統べるナイトミストの怒りを買ったということだろう。
対する“アクアフォース”も各精鋭部隊を配備。迎撃準備は万全といってよかった。

「皆、聞いてくれ」

1人1人の顔を見るように周囲を見渡しながら、檀上のジノビオスが声を上げる。

「海賊たちは総力をあげて戦に臨んでいる。今回の迎撃戦は、星輝大戦以来の大規模な戦闘になるだろう。互いに無事では済まない。如何なる策を以てしても、だ」

いつも以上に深刻そうなジノビオスの声に、将兵からどよめきが起きる。
歴戦の軍師である彼の口から放たれる言葉が、この戦の規模感を物語っている。
実際に敵を目にするよりも確かに、集まった将兵たちは事の重大さを理解した。
ほんの数分の出来事である。徐々に大きくなるどよめきを断ち斬るかのように、
ジノビオスは「だが!」とこれまでにない大きな声を上げた。

「我らの敗北はありえない!」

将兵から言葉が失われ、視線が再び檀上に集中する。隣の兵と話していた者も、
うつむき震えていた者も、皆一様に次の言葉を待っていた。もう一度、全員の顔を見渡しながら、
彼は普段通りの落ち着いたトーンで喋りだす。

「今の我らは、封印に屈した時と同じか?――否。蒼波をはじめとする数多の精鋭部隊。加えて、サヴァス中将の率いる新たな大隊。そして……大将メイルストローム殿の蒼嵐艦隊。こと戦力において、我らが敗退する道理など微塵も無い」

ここで、ジノビオスはあえて「敗北はあり得ない」と言い切った。
その言葉に、一部の将兵の顔に覇気が戻る。

「古き大望に捕らわれ、正義を見誤り、クレイ全土を手にかけようとした時と同じか?――否。今や我らは他者の正義に従う傀儡ではない。己だけの正義を見つけ貫く――大海の秩序を守る番兵となったはずだ」

視線だけを上に向けていた者たちの顔が上がる。
消沈していた室内の空気が変わり、熱気に満ち満ちていく。

「私の役割は、貴官らを死の危険が伴う戦地へと追いやることだ」

「そして」と続け、

「貴官らが敵を討ち破り、この艦に帰還する確率を全力で引き上げることだ」

静かながら、重く、深い声。

「前線に立つことを許されない私の代わりに」

ジノビオスは三度、室内を見渡した。

「皆の力を、貸してもらいたい」

部隊の長であり、稀代の名軍師とまで呼ばれた軍の大佐が、躊躇いなく部下たちに頭を下げた。
それに応える声は無く、僅かなざわめきも起こらない。たっぷり1分が過ぎ、顔を上げたジノビオスの目に映ったのは、

「……ありがとう」

彼に向かって一糸乱れぬ敬礼を行う、部下たちの姿だった。彼は軍師だ。
こういった結果になることを予想していなかった訳ではない。だが、それでも、

「貴官らの正義に、最大の感謝と敬意を」

いざ、この光景を目の当たりにした時、自分の中に何か熱いものが込み上げてくるのを感じた。
計算も打算も無い、本心からの言葉が思わず口から飛び出す。

「健闘を祈る。必ず、無事に帰還してくれ!」






………
………………
………………………………

「ふぅ……いやいや……今回ばかりは、本当に塵に還るかと思ったね」
「まったく、余裕かましてるからこうなるんだよ!」
「そんなに怒らないでくれよブラン……」

「まあいいじゃ~ん。みんな無事だったんだしさ~」
「グリ!アンタは黙ってな!」
「おぉこわ~」

「でも、ボクらが血液だけでも生きられるってことが知られてなくて良かったねぇ」
「血の状態であんま海に浸かってると、戻ったとき肌がベトベトするんだよな~」


「元の姿に戻れるまで、どのくらいかかるかなぁ」
「姿だけなら2年ってところさ。血はアタシとグリで何とかするから、アンタはしばらく大人しくしてな」


「迷惑かけるねぇ」
「……アンタがそのままだと結果的にアタシらが困るんだよ!」
「姉御、照れてる~」
「ぶっ殺すぞ!」
「ひぃこわ~」




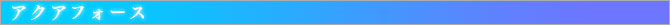
 |
轟く波紋 ジノビオス 絶対正義を提唱しながらも、兵の個性を尊重する心優しき“アクアフォース”の大佐。類稀な統率力と智謀を駆使して幾つもの死線を潜り抜けてきた名軍師。  正義とは自分自身が定めた正しき行いであると信じ、冷徹非情になる事を強要する軍の常識をあまり快く思っていない。その為、一部の佐官・将官らの不興を買い、一時は生還率が低いとされる地域へ更迭されたが、小規模の損害で同地域の制圧を完了、結果的に彼の能力を軍内部に強く知らしめることになったという。  彼は部下に「正義とは何か」と問う。 しかし答えは求めない。 その問いを投げ、自身の正義について今一度思案させる事が目的だからである。 強大なる侵略者の蛮行を阻止する為、「轟く波紋」は己の正義を執行する。 同じ思いを胸に秘めた、同じ正義を掲げる部下達と共に。 |
|
 |
 |
|
 |
逆巻く波紋 ポドロモス はるか未来の“アクアフォース”において、伝説に名を残す軍師「ジノビオス」の意志を受け継ぐ者。  ポドロモス自身はジノビオスと直接の面識はないが、大ベテランの竜将曰く「ジノビオスに最も近い精神を持つ司令官」との事。幾度もの戦いを経て、部隊の編成や司令官は変わったが、その信念は未来にもなお受け継がれている。  ――『正義とは、己が定めた正しき行いである』  他者の意志ではなく、自らの意志で定める「正しさ」とは何かを問い続けること。 それが、ポドロモスの部隊に配属された者……そしてポドロモス自身にも課せられた、永く大きな使命である。 |
|
 |
||
 |
打寄せる波紋 ミルティアディス 海軍大佐「ジノビオス」の副官を務める優秀なアクアロイド。階級は中佐。わずかだがマーメイドの因子がまぎれており、それも手伝って中性的な美しい顔つきをしている。 ジノビオスと出会うまでは、勝利のためにどんな犠牲も辞さない、軍人然とした考え方に固執していた。当然、配属された直後は、替えのきく下の者にまで気を配る彼の姿勢を毛嫌いし、時には非効率的だと指摘することもあったという。しかし、誰もが失敗すると信じて疑わなかった作戦を彼が成功に導いた時、ミルティアディスはジノビオスに対する考えを一転させた。 仲間を想い、仲間を助ける為に最良の策を練る。その心意気に、部下たちもまた全力で応える。「徳」を以てして皆をまとめ上げるジノビオスの姿勢が、ミルティアディスの探究心を強くくすぐったのである。 今では仲間想いの中佐として軍では有名な存在だが、甘すぎるジノビオスの代わりに部下を叱咤することも多く、部隊内では「鬼の中佐」と呼ばれ、恐れられているという。 |
|
 |
||
 |
荒ぶる波紋 ラビス 海軍大佐「ジノビオス」の部隊に所属する海兵。階級は伍長(あくまで形式上)。 「パヴロス」と並ぶ剣の使い手として部隊の内外で有名だが、同時にその荒っぽい素行でも悪名を知られている。  生半可な腕では扱えないという大型のハイドロ・サーベルを二刀流で振り回す筋力と剣術。 体組織を瞬時に液体へ変化させ、海に消えて移動する機動力。 しかし、突出した個の能力は、集団となると摩擦を引き起こす。そのため、常に規律や命令で押さえつけられていた。  そんなラビスであったが、現部隊に所属してからは個人による出撃が認められ、その戦闘力を遺憾なく発揮している。 「解放することで、周囲と呼応する才もある」とは、部隊長であるジノビオスの言。 荒ぶる波紋の後姿に、憧れと畏敬の視線を送る部下も、確かに育ちつつあるらしい。 |
|
 |
||
 |
高まる波紋 パヴロス 海軍大佐「ジノビオス」の部隊に所属する伍長。 飛沫のように変幻自在な高速剣の使い手。現部隊に異動する前は、高い戦闘能力を買われて執行部隊「ティアーナイト」に所属していたが、感情過多で非情になりきれない性格が災いして任を解かれてしまう。  その後、様々な部隊を転々としていたが、当時中佐であった「ジノビオス」の下で軍の思想に縛られない自由な戦い方を許され、本来の実力を如何なく発揮できるようになった。周囲の味方を巻きこないようにという配慮から単騎での突貫を好むが、読みが甘い為に危険に晒される事も多く、同部隊の「ソティリオ」によく諫められている。  その剣は水中にあっても速度を落とさず、振るえば振るう程加速する。 一見はもちろん、二度三度見たところで到底捉える事など出来ないだろう。 |
|
 |
||
 |
終焉の波紋 オレスト 海軍大佐「ジノビオス」の部隊に所属する兵士。竜の帝国に伝わる剣術の使い手で、剣術師範の任に着き、兵士達への指南を行っている。戦場への出撃はほとんどない。これは生まれつき体内の魔力が不安定で、長期にわたる作戦の遂行に耐えられないためである。  人工生命体であるアクアロイドの中には、稀に、体組織を構成する水に含まれる魔力が不安定な個体が発生する。 それらの固体は、ヒューマンで言うところの「体調不良」を起こしやすくなる。 剣に対する並々ならぬ情熱と、自分の正義を胸中に秘めながら、オレストは兵士として戦果を挙げることができずにいた。  ある戦場でジノビオスに剣の才能を見出されなければ、下級兵士として燻っているか、あるいは無茶な命令によって戦死していたであろう。  現在は訓練場で若き兵士達への指導の傍ら、海賊船の制圧など1対1の戦闘が必要な場面で出撃している。 |
|
 |
||
 |
閃く波紋 オデュッセウス 海軍大佐「ジノビオス」の部隊に所属する海兵。階級は兵長。「ソティリオ」と同世代のアクアロイドであり、候補生時代からの付き合い。外見年齢が近しいことや、同じ型の剣術を習得したことも相まって、若い頃は何かとソティリオに勝負を挑むような喧嘩っ早い少年だったという。 現在は「閃く波紋」の異名を持つ一流の剣術使いであり、1対1の試合形式であれば、「パヴロス」や「ラビス」のような単騎型の戦士にも引けを取らない。 海中で閃く剣の軌跡。音も立てず、ただ光の軌跡のみが残るその斬撃は、そうそう見切れるものではない。傷をつけられたことにも気づかぬうちに、次の傷が増えていく。意識が遠のきはじめた頃になって、ようやく相手は気づくのだ。自分の体が無数の傷で蝕まれているということに。 |
|
 |
||
 |
静かなる波紋 ソティリオ 海軍大佐「ジノビオス」の部隊に所属する兵長。 音一つ立てない剣捌きから「静かなる波紋」の異名を持つ。  雑音を嫌い静寂を好む無口な少年だが、無愛想という訳では無く、必要な時はきちんとコミュニケーションも取れる優等生。戦闘技能は高いが決定打に欠ける為、戦闘ではサポートに徹する事が多い。 突出しがちな隊員の多い部隊の制止役でもあり、戦況に関わらず単機駆けを行おうとする「パヴロス」は、いつも彼が諭しているらしい。  彼は音を嫌う。 音は心の乱れをそのまま相手に伝えてしまうから、水を通じればより顕著に伝わってしまうから。 波打つ事を忌避する波、「静かなる波紋」。 唯々静かに、音をたてない波は雑音を発する者を切り裂いていく。 |
|
 |
||
 |
始まりの波紋 アレックス 海軍大佐「ジノビオス」の細胞をもとに生成された新型アクアロイド。 階級は一等兵。 生み出されて間もない為、感情の起伏がほとんど無い。 身体を構成する水分の割合が98.5%を超える最新型で、水に溶ける身体を生かした破壊工作活動を得意とする。 戦士達が戦場に波を立てる前に状況を有利にしてくれる事から「始まりの波紋」と呼ばれる。  戦を生き延び多く物事を経験していく度、アクアロイドの心には自我が芽生えていくが、確固たる自我が築かれるまで健在でいられる兵士は多くない。  波紋とは、自分より大きな波と、堅牢な物とぶつかるだけで容易く飲み込まれてしまう儚い存在。 彼は波に飲まれ抗う術も無く消えゆく小さき者か、はたまた波をも飲み込む巨大な渦となり得る者か。 まだ見ぬ未来へ、生まれたての波が進んでいく。 |
|
 |




 |
海賊貴公子 ピノ・ノワール 直属の部下である「グリ」「ブラン」と共に世界中の海を彷徨う、齢500を数える大海賊。美しい姿で女性をたぶらかし、空腹になれば躊躇なくその血肉を喰らう生粋のヴァンパイア。“グランブルー”に所属してはいるものの、全団召集でもかからない限り、姿を現す事は無いという。  彼と彼の眷属は、肉体を失っても血液のみで生きられるという極めて稀な特性を持つ。さすがに1滴2滴ではどうしようもないが、コップ1杯分程度の血液が残っていれば、その体積に見合う姿に変化し、存在を維持することができるのである。  これまで幾度も「討伐」された経験のある彼だが、いまだ消滅には至っていない。とはいえ、ひとたび肉体を失えば、年単位で眷属たちから血液を供給してもらわないと、吸血鬼としての姿を再構成できないため、討伐直後は割と本気で落ち込むらしい。 |
|
 |
 |
|
 |
海賊麗人 ピノ・ブラン 主人である「ノワール」と共に世界中の海を彷徨う海賊。普段はノワールの希望で女性の姿をしているが、その正体は血のような羽を持つジャイアント・バット。  海の漢が裸足で逃げ出すほどの気の強さや、山賊顔負けの言葉遣いなど、男勝りな言動が目立つために腕力に物を言わせるタイプと思われがちだが、実は非常に器用で銃火器の扱いに長けている。半面、刃物は「すぐ壊れるから嫌だ」と言って、飛び道具以外はほとんど手にしないらしい。  飄々とした主人の尻拭いで戦わされる事にウンザリしている反面、彼の役に立てる事を嬉しく思う女性的な面も持っている。 |
|
 |
||
 |
駆け出し海賊 ピノ・グリ 主人である「ノワール」と共に世界中の海を彷徨う海賊。ノワールに血を吸われたことで眷属となったデーモンの少年。  ダークゾーンの生まれであり、海賊に憧れて毎日のように海を眺めていたところ、ノワールに女の子と間違えられて血を吸われてしまう。血の味で男とわかり、グッタリしてしまったノワールのために、デーモンの女性が集まる集落まで案内したことが、彼らの長い付き合いの始まりだったという。  はじめは「命令に忠実な良い子」だったそうだが、いい加減な主人の影響でどんどん適当な性格になっていき、今では主人と共に、人の神経を逆なでする悪ガキになってしまった、とはある女海賊の言。 |
|
 |